HEMS Special Page
HEMSって何?
「HEMS」は、「ヘムス」と発音します。
「home energy management system」の頭文字を取ったもので、日本語でも「ホーム・エネルギー・マネジメント(管理)・システム」と呼ばれています。
一言で説明すると、センサーやITの技術を活用して、住宅のエネルギー管理、「省エネ」「エコ」を行うシステムを指します。
なお、「BEMS」(Building Energy Management Systems:ビル・エネルギー管理システム)もあり、こちらは業務用ビルのエネルギーを管理するシステムです。
「HEMS」で実現できることは、大きく分けて2つ「表示」と「制御」です。
-
どれだけのエネルギーが、いつ、どこで、何に使用されているかを「見える化」するのが「表示」です。
-
そして、家中の機器を一括してコントロールして、自動的にエネルギー使用量を最適化したりするのが「制御」です。

最近の家電製品や自動車、太陽光発電など、センサーやコンピュータの技術を応用して、“賢い"省エネ機能を搭載した機器が増えてきています。
これらのデジタル化やネットワーク化された機器は、一般的に「情報家電」「創エネ機器」「蓄エネ機器」と呼ばれています。
「HEMS」は、そこからさらに一歩進んで、家中のこれら家電製品や他のエネルギーを使用する製品を、住宅全体として管理して「表示」し「制御」します。
あらかじめ最大使用電力を設定しておけば、家の総使用電力が設定量に達したときに、遠隔操作または自動でエアコンの温度設定を変えたり、優先順位の低い機器の電源を切ったりすることができます。
2020年省エネ基準適合住宅義務化
現代の家づくりにおいて最重要テーマの1つが「省エネ」です。
民生部門でのエネルギー消費量低減に対する社会的・国際的要請は強まる一方で、住まい手にとっても光熱費削減のメリットが大きいことから、住宅の省エネ性能は目覚ましい進化を見せています。
平成25年10月1日には改正省エネ基準(名称:25年基準)が施行され、国土交通省・経済産業省・環境省が設置する「低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議」は2020年までにすべての新築住宅を対象に新基準への適合の義務付けを決定しました。
一歩進んだ省エネ性能が求められる事となりました。
従来の基準は建物の外皮(壁や開口部など冷暖房する空間と外気を仕切る部位)の断熱性能だけで評価するものですが、新しい計算方法を採用した「外皮の断熱性能」に加えて、「一次エネルギー消費量」の2つの物差しで評価されるのが特徴です。
これまでの外皮の断熱性能は床面積あたりの数値が基準ですが、新基準では外皮面積あたりの数値が採用されました。
床面積の割に外皮面積が増える狭小住宅や複雑な形の住宅にあった不公平感が解消され、規模の大小や住宅の形状に関係なく同一の基準値が適用されました。
一次エネルギー消費量とは、建物で使う電気やガスなどのエネルギーを作り出すのに必要なエネルギーを熱量で表したもの。一次エネルギー消費量は冷暖房をはじめ、換気、照明、給湯などの設備機器の性能から算出され、太陽光パネルによる再生可能エネルギー発電機器の有無、外皮の断熱性能も評価に加味されます。
つまり、これからの家づくりは、建物自体が高断熱性能を装備していることに加え、省エネ型の設備機器を搭載していることが必須となっていきます。
これらを統合的に管理監視するHEMS。「エネルギーの見える化」の為の機器が住宅のみならず、事務所・店舗・工場・・・
エネルギーを消費する量を削減するとともに「見える化」による監視管理が必要のなります。
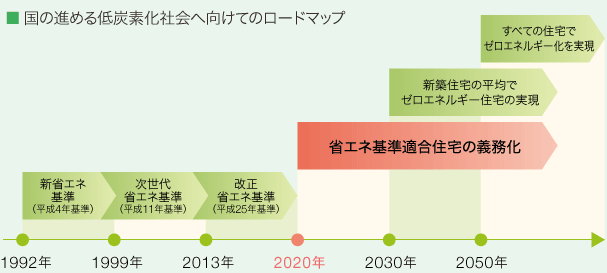
そもそも省エネ・エコって必要なの?
まず、「エコ」を名乗る製品や活動は多くても、国全体では十分な効果が上がっていないのが日本の現状です。
日本はこの20年間で「温暖化ガスを6%減らします」と世界に約束したのですが、逆に9%増やしてしまっています。
しかし約束を守らない国には、経済的に大きなペナルティを課される情勢にあります。
このため現状の日本にとっては、「排出量を減らせていない」というのが最大の問題です。環境より何より、経済的・政治的に「深刻」な状況なのは疑いようがありません。
このような動きの下地になっているのは温暖化(気候変動)です。世界中で集められた膨大なデータやスーパーコンピュータによるシミュレーションの結果、人間の活動が温暖化をもたらしている可能性が「非常に高い(95%以上)」と見られています。
残る5%の可能性を強調する「懐疑論」も見られますが、いずれも信頼性は低いです。温暖化問題が深刻であり、早急に対策が必要なのは間違いないと見られています。
しかし十分な対策をするにはエネルギーなどの社会のシステム自体を変える必要があり、巨額の費用がかかります。寄付で出来る額ではありませんので、ビジネスに組み込んでいかなければいけません。「お金を出すから、環境保護の効果を確実に挙げて下さい」という考え方に変わらなければいけないのですが、日本ではまだそのような考え方が浸透していません。
もう待てない地球環境
地球温暖化による海面の上昇
気温上昇により南極などの氷がとけることで海面が数m上昇します。バングラデシュ、モルジブなど数十カ国で国土の大半が水没することも警告されています。
日本でも海面がおよそ1メートル上昇するだけでも、水没域の東京、大阪など都市部を中心に90兆円以上の資産が失われるなど、大きな被害を受けることが予測されています。
南極の氷の10分の1が融解するだけで海面が7メートル上昇します。すでに南極の気温は2.5℃上昇し、房総半島くらいの大きさの巨大氷山がいくつも流出し始めています。今後100年で両極の気温は10℃以上の上昇が予測され、今世紀末には北極海の氷がなくなるとNASAが警告しています。
温暖化防止に向けての世界の取り組み
地球温暖化の原因は二酸化炭素(CO2)など温暖化ガスの急増です。家庭で使っている電気やガス、マイカーで消費するガソリンなどCO2は、私たちが便利で快適な生活をすることで大量に発生しているのです。
1997年の温暖化防止京都会議では、先進国全体で約5%の温暖化ガスを減らすことが決められました。
温暖化を防止するためには地球全体で60~80%の温暖化ガスの排出削減が必要です(国連IPCC報告書)。途上国の100倍以上のCO2を出している日本は91%、アメリカは96%の削減が必要です。
現在、EU(欧州連合)は削減目標を40%と大幅に上げ、ドイツやイギリスなどは既に約10%~20%の削減をしています。しかし、日本の削減目標はわずか6%。しかも逆に8%増加しています。こうした温暖化ガス排出量の増大で、このままでは温暖化防止は手遅れになると国連UNEPは警告しています。
世界的な水不足・食料危機
地球温暖化の最大の問題は、水や食料が世界的に不足してくることです。 15年後(2025年)には世界人口の大半にあたる約50億人が水不足になると予測されています。また、今後100年以内に、中国で米の収穫は8割減、ブラジルやインドでは小麦などの収穫が大幅に減少するなど、深刻な食糧不足が警告されています。(国連IPCC報告)
すでにかんばつや洪水が多発しており、こうした水不足や食糧危機の兆候が現れ始めています。
日本は、食糧の大部分を他国からの輸入に頼っており、日本は食糧危機の危険性の最も高い国なのです。
地球温暖化による気温の上昇
最近、昔に比べて夏は暑くなり、冬も暖かくなってきています。この気温変化は、地球の平均にすると100年前に比べてわずか0.5度しか上がっていません。
国連の機関(IPCC)の最新報告では、「今後100年で、最大6.4度の気温上昇」、つまりこれまでの100年間に比べて10倍以上の気温上昇が予測されているのです。
地球温暖化による影響
地球温暖化により、降雨量の変化や異常気象が多発するようになります。
植物への影響も大きく、森林の消滅や生物種の絶滅などが予測されています。50年後にはアマゾンの森林は砂漠化すると予測もあります。(イギリス政府報告)
また世界各地で異常気象が多発するなど、すでに地球温暖化の影響は始まっているのです。
住宅、集合住宅、オフィス、工場、町、街⇒エネルギーの「見える化」
HEMSは必須の条件となりました
だからHEMS[ViewE]が必要です。
エコの必要性レポート
 |  |  |  |
|---|---|---|---|
 |  |  |  |